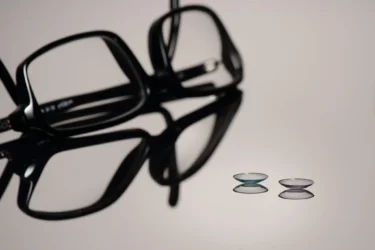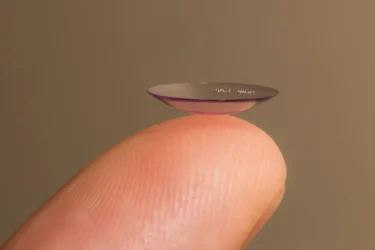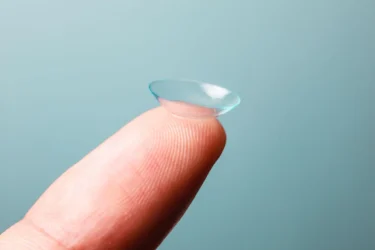「最近、子どもが黒板の文字を見づらそうにしている」「スマホを見る時間が長くなって視力が心配」といった悩みを持つ方も少なくありません。
近視は現代人にとって非常に身近な目のトラブルのひとつであり、年齢を問わず増加傾向にあります。
特に子どもの近視は進行が早いため、早めの理解と対策が重要です。
この記事では、近視とは何かという基本的なことから、子どもの近視について、進行抑制のための治療法、さらに近視が進行した場合のリスクなど幅広く解説します。
大人の場合も子どもの場合も、目の健康を守るための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
近視とは?

近視とは、遠くのものがぼやけて見える視力の異常で、現代人に非常に多く見られる目のトラブルです。
黒板の文字がぼやけて見えたり、道路標識が見えにくくなったりするのは、近視の典型的な症状です。
本来目に入ってきた光は、目の奥にある網膜というスクリーン状の組織の上で焦点を結ぶことで、はっきりとものが見える仕組みです。
しかし、近視になると、この焦点が網膜よりも手前で合ってしまうため、遠くのものがぼやけて見えるのです。
近視は治るのか
近視には、軸性近視と屈折性近視(仮性近視)という2種類があります。
軸性近視は目の奥行き(眼軸)が伸びてしまうことで生じるもので、一度伸びた眼軸を元に戻すことはできません。
つまり、治療で視力を回復させることは難しいとされています。
一方、屈折性近視は、水晶体が過剰に緊張して分厚くなり、一時的にピントが合いにくくなる状態です。
このタイプは、点眼薬や目の使い方を改善することで回復が期待できるため、『治る近視』とも呼ばれます。
近視のタイプを正確に診断するには、眼科で眼軸の長さを測定する必要があります。
近視の原因

近視の原因には、大きく分けて遺伝的要因と環境的要因があります。
どちらか一方だけでなく、両者が複合的に関与して近視になるケースが多く見られます。
遺伝的要因
近視は、家族に同じ症状を持つ人がいると発症しやすくなる傾向があります。
片方の親が近視の場合、子どもが近視になる確率は約2倍、両親ともに近視の場合は5倍以上とも言われています。
特に軸性近視は遺伝的な影響が大きく、進行性であり、病的近視へつながることもあります。
なお、遺伝的な近視の多くは乳幼児期ではなく、小学校入学以降に現れることが多いとされています。
環境的要因
日常生活の中で、目を酷使するような習慣も近視の発症・進行に影響を与えます。
読書や勉強、スマホ・パソコンなどが環境的要因として挙げられます。
読書・勉強
長時間にわたって机に向かい勉強や読書をすることで、目の調節機能が疲れ、ピントを合わせるための筋肉(毛様体筋)が緊張しやすくなります。
この緊張が続くことで、一時的な屈折性近視や軸性近視の進行につながる可能性があります。
スマホ・パソコン
最近では、スマートフォンやタブレット、ゲーム機などの画面を近距離で長時間見ることが近視進行に大きな影響を与えていると指摘されています。
屋内で過ごす時間が長くなり、自然光を浴びる機会が減ることも近視のリスクを高める要因のひとつです。
子どもの近視について

近年、子どもの近視が急増しており、深刻な社会的課題となっています。
文部科学省の『学校保健統計(令和6年度)』によると、裸眼視力1.0未満の児童・生徒の割合は、小学生で3割以上、中学生で約6割、高校生では約7割と報告されており、年齢とともに近視の割合が高くなる傾向があります。
子どもの近視が進行する原因はいくつかあります。
遺伝的な要因のほか、屋外活動の不足、睡眠不足、スマートフォンやタブレットなどの使用時間の増加など、日常生活に密接に関わる環境的要因が指摘されています。
なかでもデジタル機器の普及により、子どもたちが屋内で長時間近くを見続けることが増え、近視の急増に拍車をかけていると考えられています。
子どもの近視の予防法
子どもの近視の進行を防ぐには、日常生活の中で意識的に環境を整えることが大切です。
特に、屋外で過ごす時間の確保と近くを見る作業への配慮が、予防において重要なポイントです。
外で遊ぶ時間を作る
屋外で過ごす時間が少ない子どもほど近視になるリスクが高いと言われています。
屋外活動中に浴びる自然光は、近視の進行を抑える効果があるとされ、1日あたり少なくとも2時間程度の外遊びが望ましいとされています。
また、直射日光に限らず、木陰や建物の影といった屋外の明るさでも近視予防に効果的な照度が得られる場合が多いため、日差しの強さを避けて過ごすことができます。
外遊びの効果は単に光を浴びることではなく、目の緊張を和らげる・身体を動かす・精神的リフレッシュといった複合的な要素が組み合わさって近視予防に寄与しているそうです。
近くを見る作業の注意点
読書や書き物、デジタル機器の使用など、近くを見る作業は現代の子どもたちにとって避けられない日常的な活動です。
完全に避けることは現実的ではないため以下のような点に注意が必要です。
- 見る距離の目安:目と本や画面との距離を30cm以上離す
- 作業時間の工夫:30分ごとに遠くを見て目を休める
- 作業環境の明るさ:読書は照度300ルクス以上の明るい場所で行う
- デジタル機器の扱い:スマホ・ゲーム機の使用時間が長くならないようにする
近視予防のためには、生活の中でできる工夫が大切です。
近視の進行抑制方法

近視は、一度進行すると元の状態に戻すことは難しいとされています。特に眼軸が伸びてしまった場合、視力矯正だけでは視機能を完全に回復することができません。
そのため、進行をできるだけ抑えることが重要です。
ここでは、近視の進行を遅らせる代表的な方法と、それぞれの特徴や注意点について紹介します。
眼鏡を装着する
眼鏡は視力矯正の一般的な方法です。
装着が容易で、子どもでも簡単に使える点が大きなメリットです。また、視力に応じて柔軟に度数を調整できるのも利点です。
一方で、スポーツや活発な遊びの際には外れてしまったり、破損のリスクがあったりするため、場面によっては不便を感じることもあります。
また、眼鏡の位置がずれやすく、視線の使い方によっては矯正効果が十分に得られにくいことがあります。
コンタクトを装着する
コンタクトレンズは、見た目の変化が少なく、広い視野でクリアな視界が得られる点が特徴です。
特に度数が強い近視の場合でも、しっかりと視力矯正できるという利点があります。
ただし、正しい装着方法や衛生管理を守らなければ、眼のトラブルにつながるおそれもあります。
特に小中学生が使用する場合には、親のサポートや定期的な眼科でのチェックが重要です。
オルソケラトロジー治療
オルソケラトロジーとは、夜間就寝時に専用のハードコンタクトレンズを装着し、角膜の形を一時的に変えることで日中の視野を裸眼で保つ治療法です。
軽度から中程度の近視に適応され、起床後はレンズを外して過ごせる点が大きな特徴です。
オルソケラトロジーは、大人の場合は進行抑制にはならず、視力回復方法として使用されます。
見た目に影響せず、スポーツ時にも気にならないという利点がある一方で、高額な治療費や度数の変動により眼鏡の併用が必要になるケースがあります。
また、使用に際しては毎日のレンズ管理と正しい装着手順の理解が不可欠です。
低濃度アトロピン点眼
アトロピン点眼は、近視の進行を抑える医療用の点眼治療です。
従来の1%濃度では副作用が強く、まぶしさや近くが見えにくくなるといった問題がありましたが、現在では0.025%などの低濃度アトロピンが開発され、副作用が出にくくなりました。
低濃度アトロピン点眼は、就寝時に1滴点眼するだけという簡便さが特徴で、副作用が少ないため、日常生活への影響があまりないとされています。
なお、自由診療に該当するため、保険適用はありません。
レッドライト治療
レッドライト治療は、650nmの波長を持つ赤色光を1日2回週5日、3分間ずつ眼に照射することで眼軸の伸びを抑えることを目的とした新しい治療法です。
専用の機器を使って自宅や医療機関で短時間で行えるため、子どもにも取り入れやすいのが利点です。
現時点で重篤な副作用は報告されておらず、今後の研究成果が期待される治療方法です。
近視が進むとどうなる?

子どものころから始まった近視が進行すると、強度近視と呼ばれる状態になることがあります。
近視が進むことで眼軸が通常よりも長くなり、眼球全体に過度な負担がかかります。
結果として、網膜や視神経、脈絡膜などの組織が引き延ばされて薄くなり、機能が損なわれやすくなります。
強度近視は見えにくいという問題だけでなく、進行することで重大な眼疾患を引き起こすリスクが高くなるため、眼科での定期的なチェックが大切です。
ほかの眼疾患につながることも
進行した近視は以下のような重篤な眼疾患のリスクを高める可能性があります。
- 緑内障:視神経が障害されて視野が徐々に欠けていく病気
- 近視性視神経症:眼球後部に後部ぶどう腫が形成され視野の欠損が進行していく病気
- 白内障:水晶体が濁る病気。強い近視では40代ごろに発症する場合もある
- 網膜剥離:網膜に穴ができ、網膜が剥がれていく病気
- 近視性黄斑症:眼球の後方が引き伸ばされることで黄斑部にさまざまな異常が起こる状態
定期的な眼科受診により、病気の早期発見と進行の抑制を行うことができます。
子どもの近視進行を放置せず予防に積極的に取り組むことで、重篤な眼疾患の予防にもつながります。
近視になってしまったら

一度近視になってしまうと、伸びてしまった眼軸を戻すことができません。
ただし、軽度の近視は現代のライフスタイルに適した面もあります。
近くにピントが合いやすく、読書やパソコン作業に集中しやすいとも考えられるため、自分の生活スタイルや視力の状態に合わせた付き合い方をすることも大切です。
また、近視が進行することで眼疾患のリスクが高まるため、進行を防ぐための工夫と目の健康管理をすることを心がけましょう。
近視の対策
近視の進行を抑制するためには、適切な視力矯正と定期的な眼科受診が推奨されます。
両目で視力が0.7を下回る場合は、視力矯正を検討すべきタイミングです。
ただし、視力や眼の状態は年齢や生活環境によって変化するため、眼鏡をつくった後も定期的に眼科を受診し、自分の眼の状態を把握しておくことが重要です。
目の健康を守るためにしたいこと
目の健康を維持するには、日常の過ごし方や環境が大きく影響します。
以下のポイントに注意しながら目にやさしい生活を意識しましょう。
| 対策項目 | 内容 |
|---|---|
| 屋外で過ごす時間を確保する | 1日2時間、週14時間の屋外活動を心がける |
| 十分な睡眠をとる | 睡眠不足や生活リズムの乱れは近視進行のリスクになる |
| 作業環境の明るさを見直す | 読書や勉強時には部屋の照明に加え、手元ライトの使用を推奨 |
| 目との距離を保つ | 目と本やスマホなどは30cm以上距離をとる |
| こまめに目を休ませる | 30分作業したら5分休憩し遠くを見る |
| 栄養にも気を配る | にんじんやトマトに含まれる抗酸化成分を摂取しつつ、バランスの良い食事を心がける |
目の健康のためにも日常の過ごし方には気を付けて過ごすことや定期的な眼科検診に通うことが重要です。
まとめ
近視は一度進行すると自然に治ることはありませんが、正しい知識と対策によって進行を抑えることは可能です。
近視の進行を防ぐためには、眼鏡やコンタクトレンズによる矯正のほか、オルソケラトロジーや点眼薬、レッドライト治療といった新しい治療法も選択できます。
近視を放置すると、重篤な眼疾患にもつながるおそれがあるため、日常生活の過ごし方に気を付けるとともに、定期的な眼科検診が大切です。
『タワーリバーク眼科』では、新しい治療法である低濃度アトロピン点眼やレッドライト治療も行っています。
川崎駅北口改札直結とアクセスも良好で、土曜や日曜も診察を行っております。
近視について気になることがありましたら、ぜひ『タワーリバーク眼科』へご相談ください。