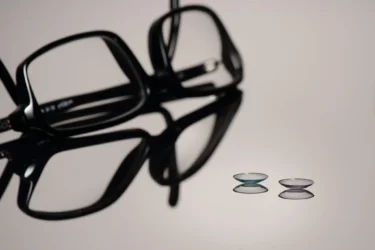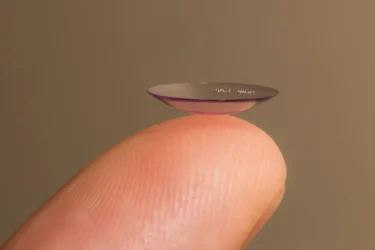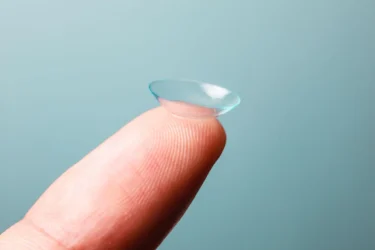スマートフォンやパソコンの長時間使用によって、子どもから大人まで近視に悩む人は少なくありません。
一度進行してしまうと元に戻すのが難しいと言われる近視ですが、仮性近視であれば改善の可能性があり、進行を抑える方法もあります。
この記事では、近視の原因から自力での改善方法、矯正手段、進行予防のポイントまで、わかりやすく解説します。
ご自身の目の状態やお子さんの近視で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
近視とは?

目はカメラのような構造をしており、光を取り入れてピントを合わせ、映像を認識するしくみになっています。
角膜と水晶体がカメラのレンズ、網膜がフィルムの役割を担っています。
近視とは、このピントが網膜よりも手前で合ってしまう状態のことを指すため、近くのものは見えるのに、遠くがぼけて見えるという特徴があります。
特に強い近視の場合は、ものを極端に近づけなければピントが合いません。
このような状態になる主な理由は、目の中で異常が起こっているためです。なかでも、仮性近視と軸性近視が代表的です。
仮性近視
仮性近視は、一時的にピントを調整する機能がうまく働かなくなることで起こる近視です。
私たちの目は、近くを見るときに水晶体を厚くしてピントを合わせています。
しかし、長時間スマートフォンやパソコンを見続けると、ピント調節に関わる筋肉が緊張したままになります。
この状態が続くと、遠くを見る時に水晶体が元の薄い状態に戻れず、ピントが網膜の手前で合ってしまうのです。
仮性近視は特に子どもや若年層に多く見られ、生活習慣の改善や適切な治療によって回復が期待できるのが特徴です。
軸性近視
軸性近視とは、眼球の奥行き(眼軸)が通常より長くなることで、ピントが網膜より手前にずれてしまう近視です。
これは構造的な変化によるもので、一度伸びた眼軸は自然に元に戻ることはありません。
軸性近視は遺伝的な要因に加えて、長時間にわたって近距離を見る生活習慣によって進行することがあります。
近くにピントを合わせた状態が続くことで、目の成長に影響を与え、眼軸が伸びてしまうと考えられています。
近視の原因
近視の原因には、大きく分けて遺伝的要因と環境的要因の2つがあります。特に近年増加している子どもの近視には、生活環境が大きく関わっていると指摘されています。
| 分類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 遺伝的要因 | 遺伝子によって近視のなりやすさが決まる | ・両親のどちらかが近視だと子どもの近視リスクが約2倍
・両親ともに近視だと約5倍のリスク ・病的近視は遺伝要因が強い |
| 環境的要因 | 生活習慣や使用環境が視力に影響する | ・スマホやパソコンなど近距離作業の増加
・長時間の読書やゲーム ・屋外活動の不足 |
| 長時間の近距離作業が毛様体筋を緊張させ、仮性近視の原因になる | 水晶体が厚い状態で固定され、遠くにピントが合わなくなる |
遺伝的な素因を持っていても、環境を整えることで近視の進行を抑えることが可能です。
特に、成長期の子どもにとっては、生活習慣の改善や屋外活動の確保が重要な予防策となります。
近視を自力で治す方法はある?

近視のタイプによっては、視力の回復が期待できるケースもあります。
特に仮性近視と呼ばれる一時的な近視であれば、適切な対処によって視力が改善することがあります。
ここでは、自力で近視を改善できる可能性があるケースや、日常生活で取り入れやすい視力回復トレーニングについて解説します。
仮性近視ならできる可能性がある
仮性近視とは、目の中にあるピント調節の筋肉(毛様体筋)が緊張し、うまく元に戻れないことで起こる一時的な視力低下のことです。
近くのものを長時間見続けると、この筋肉が疲れて固まり、水晶体の厚みが変化しづらくなり、遠くのものにピントが合いにくくなり、視力が落ちたように感じます。
ただし、この場合は眼軸に変化がないため、筋肉の緊張がほぐれれば、視力が回復する可能性があります。
逆に軸性近視は、眼球そのものが前後に伸びてしまうことで起こる近視で、構造的な変化のため自然に元に戻すことはできません。
軸性近視は、眼鏡やコンタクトレンズ、あるいは手術といった矯正方法が必要になります。
仮性近視かどうかを判断するには、眼科での検査が必要です。
特に成長期の子どもの場合は、仮性近視のうちに生活習慣を見直し、適切な対応を行うことが非常に重要です。
視力回復トレーニング
仮性近視の場合、ピント調節に関わる筋肉をほぐすことで視力の改善が期待できます。
以下に、日常生活で実践できる視力回復トレーニングを紹介します。
これらのトレーニングは即効性があるものではなく、継続が大切です。
また、あくまで仮性近視や眼精疲労の軽減を目的とした補助的な方法として行い、眼科の検診も受けるようにしましょう。
遠近体操法
手元と遠くの対象物を交互に見ることで、毛様体筋の緊張と弛緩を繰り返し、ピント調節機能をリラックスさせる効果が期待できます。
方法は以下のとおりです。
- 手を伸ばして親指を立て、近くの目標として見る
- 遠くにある目標物を決めて交互に見る(各10秒程度)
- 片目ずつ10セットほど繰り返す
2分以内でできるトレーニングのため、空いている時間にこまめに行いましょう。
意識的なまばたき
まばたきを意識的に行うことで、外眼筋や目の周りの筋肉がほぐれ、血流も改善します。
また、ドライアイの予防にもつながります。
眼球をゆっくり回す
両目で大きな円を描くように動かすことで、目の周辺の筋肉をストレッチします。
時計回り、反時計まわりにそれぞれ2~3周ずつ、ゆっくりと行うのがポイントです。
近視の矯正方法

眼科では近視の見えにくさを補ったり、進行を抑えたりするためのさまざまな矯正治療を受けられます。
ここでは、代表的な方法をそれぞれの特徴や注意点とともに解説します。
眼鏡
眼鏡は最も一般的な近視矯正方法です。
視力に合わせたレンズを使って網膜上にピントを合わせることで、遠くのものもはっきり見えるようになります。
日常生活の中で必要なときだけ使用することもでき、装用に慣れる必要もないため、誰でも利用しやすいのが大きなメリットです。
ただし、激しい運動の妨げになることや、眼鏡のずれによって視界が不安定になることもあるため、使用環境によっては不便に感じる場合があります。
コンタクトレンズ
コンタクトレンズも視力矯正に有効な方法です。
視野が広く、眼鏡よりも自然な見え方になる点が特徴です。また、見た目に影響がないことから、外見を気にする人にとってはメリットがあります。
ただし、扱い方を誤ると角膜を傷つけるリスクがあり、特に子どもに使用させる場合は、正しい装着方法やケアの習慣をきちんと身に着けることが前提です。
目薬
リジュセアなどの低濃度アトロピン点眼薬は、近視の進行を抑える治療として注目されています。
ピント調節に関わる筋肉の緊張をやわらげることで、眼軸の伸びを抑える効果が期待できます。
リジュセアミニ点眼液は1回分ずつの使い捨てパッケージのため、防腐剤を入れずに長期使用が可能になりました。
日本では自由診療扱いで保険適用外となり、費用負担がある点や、効果には個人差があることに注意が必要です。
副作用は少ないとされていますが、散瞳効果と調節麻痺効果によるまぶしさと手元のぼやけがあるため、必ず就寝前に点眼しましょう。
オルソケラトロジー治療
オルソケラトロジーは、就寝中に特殊なハードコンタクトレンズを装着して角膜の形を矯正し、日中は裸眼で生活できるようにする治療法です。
軽度から中程度の近視までが対象であり、継続的な装用により近視の進行を抑える効果も期待できます。
メリットには手術が不要で日中裸眼で過ごせる、治療を中止すると元に戻る可逆性があることです。
一方、レンズケアの手間やコスト、ハロー・グレアといった見え方の違和感、感染症リスクなどのデメリットもあるため、事前の十分な説明と理解が必要です。
レッドライト治療
レッドライト治療とは、ごく弱い赤色光線を目に照射することで近視を抑える新しいアプローチです。
一部の研究では、眼軸の伸びが抑えられたり、場合によっては若干の短縮が見られたという例もあります。
日本ではまだ導入している医療機関が限られており、保険適用外の自由診療です。
手術
手術による近視矯正方法には、レーシックやICL(眼内コンタクトレンズ)などがあります。
レーシックは角膜の形状をレーザーで変えることで屈折異常を補正する方法です。
ICLは眼内に特殊なレンズを挿入する方法で、角膜を削らないため可逆性が高いのが特徴です。
レーシック、ICLともに自費診療となり、術後の合併症や見え方の変化などのリスクもあるため、慎重な検討と信頼できる施設での受診が推奨されます。
近視の進行を予防するには

近視は一度進行してしまうと自然に治すことは難しいため、進行をできるだけ抑えるための予防策が重要です。
特に子どもの場合は、生活習慣や環境に影響されやすく、適切な対応を早めに行うことが将来の視力維持につながります。
生活習慣の改善
生活習慣を改善することで、近視の進行を抑えられる場合があります。
具体的には以下のような点を意識しましょう。
| 項目 | 具体的な対策 |
|---|---|
| 視距離の確保 | 手元のものを見る時は30cm以上離す |
| 姿勢の改善 | 寝転んで本を読まない・顔を近づけない |
| 明るさの調整 | 読書時は300ルクス以上の照明を確保 |
| 目の休憩 | 30分ごとに5分休憩を心がけ、遠くを見る |
| 屋外活動の習慣化 | 1日40分~2時間程度外で遊ぶ・運動する |
| スマホ・ゲーム使用制限 | 長時間の連続使用を避ける |
| 睡眠と生活リズム | 早寝早起き・朝食をきちんと食べる |
特に子どもの生活習慣は親がきちんと対策し、早めに進行を抑える予防策をとりましょう。
定期的な眼科検診
どれだけ生活習慣に気を配っていても、視力の低下を自覚しづらい子どもの場合や初期段階の近視を見逃してしまうことがあります。
視力が気になった時や学校検診で異常を指摘された場合は、必ず眼科を受診し、正確な診断を受けるようにしましょう。
特に仮性近視かどうかの見極めには、眼軸長の測定や調節麻痺を利用した検査が必要です。
正しい対処を行えば、回復や進行抑制が可能な場合もあります。
子どもの近視抑制は早めの治療が大切
子どもの視力は、成長とともに変化します。特に近視は小学生の間に急激に進行する傾向があるため、早期の対応がとても重要です。
低濃度アトロピン点眼薬やオルソケラトロジー治療、レッドライト治療などの方法を受けることも近視抑制に効果が期待できるため、まずは眼科の受診をおすすめします。
まとめ
近視は一度進行すると完全に元の視力に戻すのが難しいとされていますが、原因を理解し、早めに適切な対策をとることで進行を抑えることは可能です。
仮性近視であれば、生活習慣の改善やトレーニングで視力が回復することもあります。
また、眼鏡やコンタクトレンズ以外にもオルソケラトロジーなどの新しい矯正方法も出てきており、個人に合った選択が重要です。
特に子どもの近視は早期対応が大切なため、日々の生活習慣を見直し、定期的な眼科受診を習慣づけることで目の健康を守ることにつながります。
『タワーリバーク眼科』では、お子さんから大人まで、近視抑制治療を行っています。
新しい矯正方法である、低濃度アトロピン点眼やレッドライト治療も取り入れておりますので、近視が気になる方はぜひご相談ください。