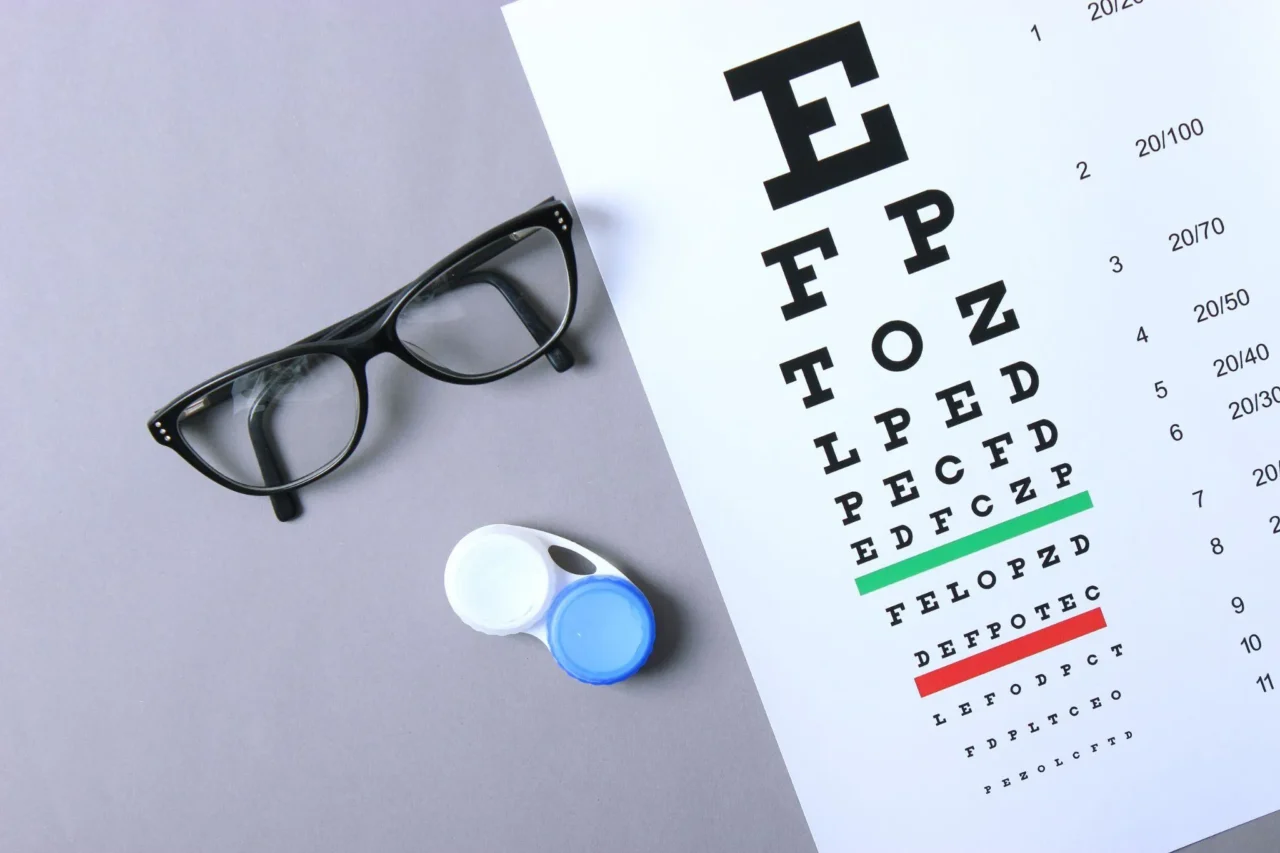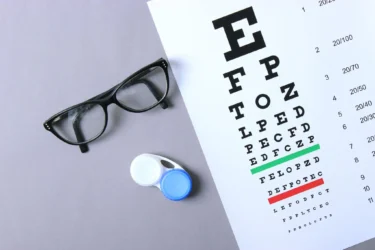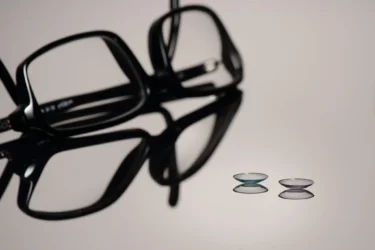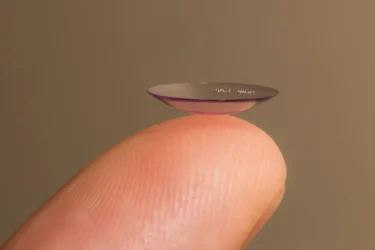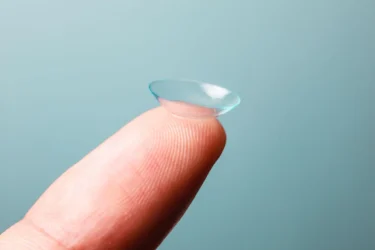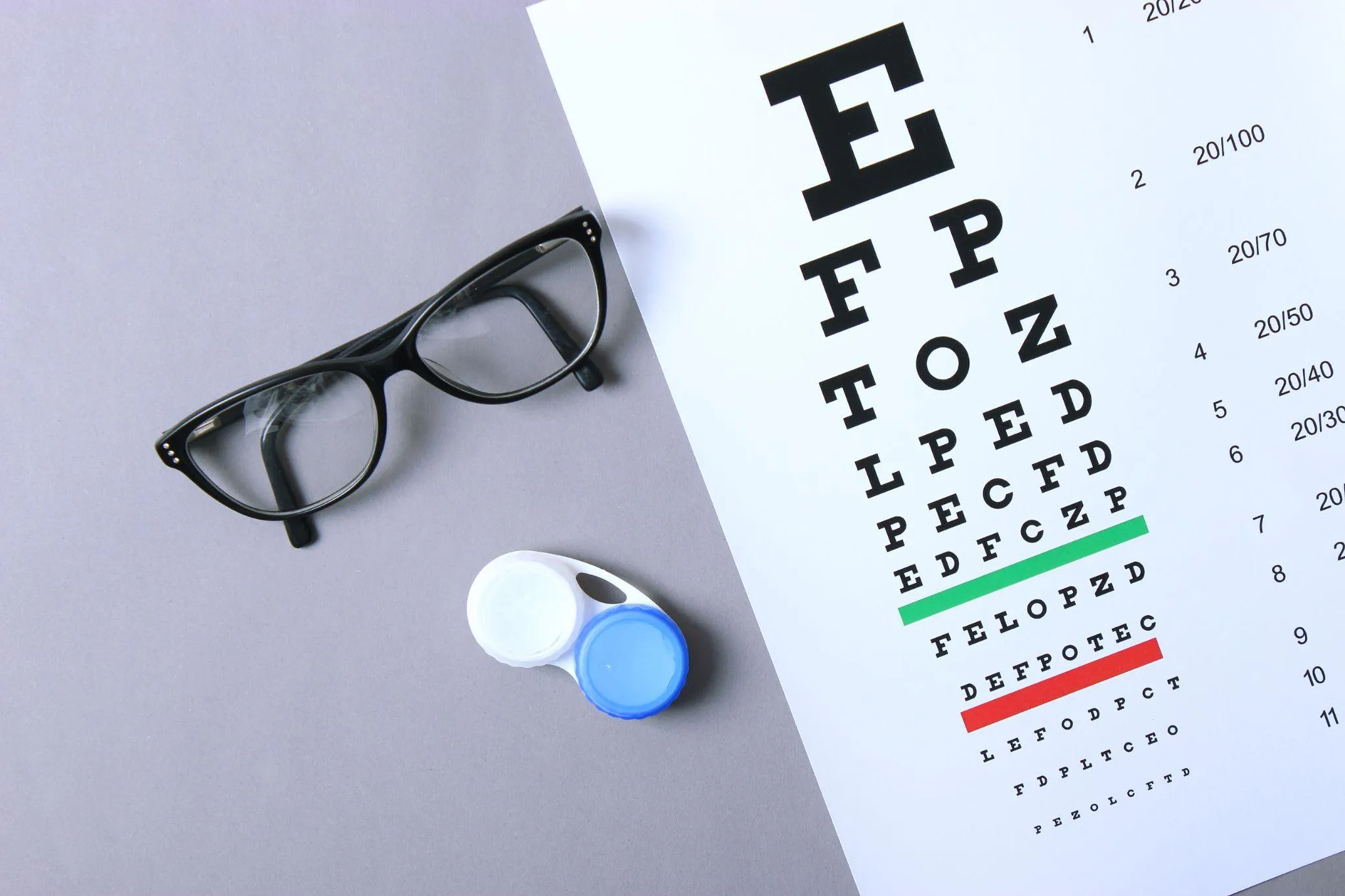
視力の低下や目の異常を感じたときに眼科を受診する方は多いかもしれませんが、症状がなくても眼科を受診できることはご存じでしょうか。
視力に問題がない方は眼科に馴染みが薄く、「眼科に行ってなんて言えばいいのか?」と考えてしまい、受診するのをためらってしまうかもしれません。
定期検診を受けることは、目の病気の早期発見や予防のため非常に重要です。
この記事では、眼科の定期検診の受け方や検査の内容、受診のタイミングについて、詳しく解説します。
受付でなんて言えばいいのか迷っている方、検査を受けるタイミングがわからない方は、ぜひ参考にしてください。
眼科の定期検診は目の病気や異常がなくても受けられる

眼科の定期検診は、目に異常を感じていない方でも受けることができます。
自覚症状がないうちに進行する目の病気もあるため、早期発見・早期治療するためにも定期検診が欠かせません。
受付でなんて言えばいい?
特に症状がない場合、受付で「なんて言えばいい?」と迷ってしまうかもしれません。
そんなときは、以下のように伝えると検査を受けに来院したことが伝わり、スムーズです。
- 定期検診を希望している
- 目の健康チェックのために検査を受けたい
糖尿病や高血圧などの持病があり、かかりつけ医から指示されて受診した場合は、その旨を伝えましょう。
ただし、クリニックによっては検査を受けるには予約が必要な場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
検査時の持ち物・注意点
定期検診を受けるときの持ち物は、以下の通りです。
- マイナンバーカード(内蔵したスマホでも可)
- メガネ(現物と使用データ)
- コンタクトレンズ(箱に記載されているデータ部分)
- 健康診断結果
- 必要に応じて紹介状を持参
メガネはかけていて構いませんが、コンタクトレンズは検査時に外す必要があり、帰宅時もしばらく装用が難しいため、検査の日はコンタクトケースやメガネを用意しておいた方がよいでしょう。
瞳孔を開いて眼底を見る検査を行う場合、瞳孔が元に戻るまで見え方が通常と異なるためメガネやコンタクトレンズを使用しても思うように見えなくなります。
いつもよりまぶしさを感じたり、遠近感が取りにくかったりする状態です。
瞳孔が通常に戻るまでには個人差がありますが、3~6時間ほどかかります。
検査を受ける際は、車での来院は控え、公共交通機関を利用するか、家族に付き添いを頼んでおきましょう。
定期検診の頻度
日本眼科医会では、40歳を過ぎたら1年に1回程度の定期検診を推奨しています。
(参照:「40歳を過ぎたら受けよう!眼底検査 目の健康を守るために」公益社団法人 日本眼科医会)
40歳を境に目の病気(緑内障や黄斑疾患など)の発症率が上がることが理由ですが、定期検診により早期発見・早期治療ができれば視力を維持できる可能性が高まります。
1年に1回の定期検診を受けることで、将来的な目の病気を防ぐことにもつながります。
また、目の疾患に影響する持病(糖尿病や高血圧など)がある場合や、目の病気の既往歴がある方は、医師の指示に従い頻度が変わることもあるため、注意が必要です。
定期検診の費用
定期検診の費用は、クリニックや症状の有無などにより異なりますが、保険診療(3割負担)で2,000~3,000円ほどが目安です。
ただし、検査内容や追加項目によっても前後することがあるため、事前に確認しておきましょう。
なお、通常の定期検診では行わないオプションの検査は自費診療となる場合もあるため、注意が必要です。
眼科の定期検診の重要性

目の病気の多くは、初期には自覚症状がほとんどなく、気づきにくいものです。
目に症状がなくても、例えば頭痛の原因が目の病気だったということもあります。
緑内障や糖尿病網膜症、加齢黄斑変性などは、気づかないうちに進行することがあるため、眼科の定期検診を受けて早期発見・早期治療が視力を守るために重要です。
自覚症状がないまま長期間病気が進行すると、痛みや充血、視力の変化などの症状が起こることがあり、その時点で受診する方も少なくありません。
しかし、目に異常が出てからでは治療開始が遅れてしまいます。
定期的に目の検査を受けていれば目の状態の変化をすぐに把握でき、異常があった場合は早期に治療を開始できます。
視力低下や失明のリスクを防ぎ、目の健康を維持するためにも、定期検診を受けることが大切です。
眼科の定期検診の検査内容|基本

眼科の定期検診はどのような検査をするのか、あらかじめ知っておくと不安が軽減できます。
ここでは、多くの眼科で行う基本の検査内容を詳しく解説します。
視力検査
視力検査は、裸眼視力と矯正視力(メガネやコンタクトをつけた視力)の両方を測定して、視力の状態を確認します。
どこまで小さな指標が見えるかをチェックして、視力の測定をする検査です。
視力の左右差や視力低下がみられる場合は、さらに詳しい検査をすることもあります。
眼圧検査
眼圧検査は、目の内圧(眼圧)を測定する検査で、緑内障の発見にも役立つ検査です。
空気を当てるタイプ(非接触)と、機器を角膜に接触させるタイプがあります。
個人差がありますが、眼圧の正常値は10〜21mmHgとされています。
眼底検査
眼底検査は、視神経や網膜の状態を確認する検査です。
網膜の血管から、全身の動脈硬化の状態や糖尿病網膜症の発見なども診断できます。
一般的には散瞳剤(瞳孔を広げる点眼薬)を使用して、30分ほど待機してから行います。
瞳孔が元に戻るまでは3~6時間ほどかかるため、検査後は車の運転は控えてください。
問診
問診では、現在の症状や既往歴、手術歴、生活習慣、家族歴などを医師が確認します。
状態によってはより詳細な検査を行うこともあるため、些細なことでも視力の変化やドライアイなども伝えることで、適切な検査や診断につながります。
治療が必要な場合は、今後の治療計画を立てるためにも問診での聞き取りが重要です。
眼科の定期検診の検査内容|追加検査
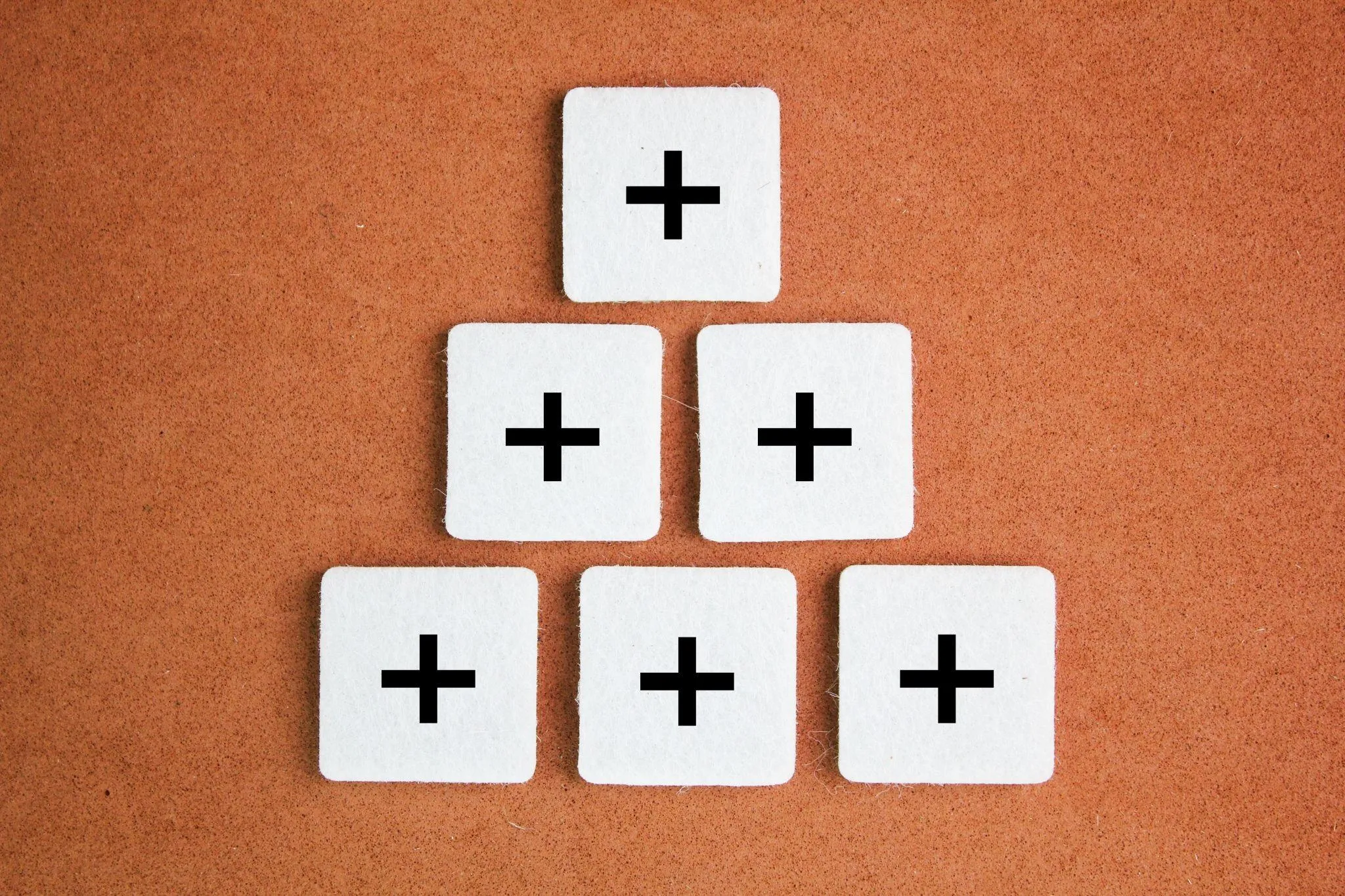
基本の検査項目以外にも、定期検診では必要に応じて追加検査が行われます。
年齢や気になる症状により、詳しい検査を追加で行った方がいいこともあるため、検査の種類を知っておくといいでしょう。
屈折検査
屈折検査は、近視、乱視、遠視の程度を測定する検査です。
目に入る光の屈折状態を測り、視力の状態を客観的に評価します。
屈折検査自体は基本の検査項目に入っているクリニックも多く、この検査結果を参考に視力検査を行います。
視野検査
視野検査は、視野の欠けや視界に見えにくい部分がないか、見える範囲を確認します。
緑内障の発見には欠かせない検査で、視神経の異常がある場合は視野の変化がわかります。
他にも網膜疾患や視神経疾患、脳疾患の診断にも必要な検査です。
細隙灯顕微鏡検査
細隙灯(さいげきとう)顕微鏡検査は、角膜や水晶体、硝子体、虹彩、結膜など、前眼部を詳しく観察する検査です。
スリットランプと呼ばれる機器を使用して帯状の光を当てることで、眼球表面の細かな傷や炎症も発見できます。
白内障の診断の際に不可欠な検査で、年齢により毎回の定期検診で行われることもあります。
OCT検査
OCT(光干渉断層計)検査は、網膜や視神経の断層画像を撮影する精密検査です。
使用する機器によりますが、血管形態(血管の詰まりや新生血管の発生)を画像化することもできます。
緑内障や黄斑疾患、網膜疾患など、網膜に関する病気の早期発見に欠かせない重要な検査です。
角膜形状検査
角膜形状検査は、角膜の形を立体的に測定して、不正乱視や円錐角膜の有無を確認する検査です。
白内障の手術前評価や、レーシックやICLなどの屈折矯正手術の適応検査としても行われます。
メガネで矯正できない細かな変化を測定することができ、メガネやコンタクトレンズ、屈折矯正手術の中で適した方法を診断するためにも必要です。
角膜内皮細胞検査
角膜内皮細胞検査は、角膜の内側にある内皮細胞の数や状態を確認する検査です。
細胞数が減ると、角膜浮腫を生じる可能性があります。
角膜内皮細胞は細胞分裂せず加齢により減少していくため、手術前に細胞数を測定しておくことで、白内障手術の影響や角膜移植などの手術後の予測や診断に役立ちます。
また、コンタクトレンズの長期使用によっても細胞が減少するため、定期的に検査をしておくことが大切です。
眼科の定期検診を受けるタイミングは?

眼科の定期検診はいつ受けたらいいのか、タイミングがわからない方も少なくありません。
受けるべきタイミングはいくつかあるため、ポイントを含めて詳しく解説します。
コンタクトレンズやメガネを作るとき
コンタクトレンズやメガネを作るときは、眼科で検査を受けましょう。
視力に合った度数のレンズを選ぶためには、正確な視力測定が必要です。
特に初めてのときや、新しいものを作るときは、合わないレンズで目に負担をかけないように、きちんと眼科で測定してください。
また、コンタクトレンズの長期使用は角膜に影響を与える可能性があるため、状態にもよりますが、3~6ヶ月ごとなど、医師の指示に従い定期検診を受けましょう。
目の異常や気になることがあるとき
目の異常や気になることがあるときは、眼科を受診してください。
目のかすみや充血、乾き、疲れやすさを感じるなど、軽い症状でも病気のサインかもしれません。
我慢や様子見をせずに早めの受診をすることで、重大な目の病気が発見されることもあります。
学校や会社で詳しい検査を勧められたとき
学校や会社で行われる健康診断で「再検査」や「眼科受診をすすめる」などの結果が出た場合は、できるだけ早めに眼科を受診して検査を受けてください。
どのような病気の兆候があるかまでは、健康診断ではわからないこともあります。
眼科で詳しい検査を受けることで、視力に影響が出る前に病気を発見できる可能性が高まります。
持病がある・家族に目の疾患歴がある
目に影響がある持病がある方は、定期検診を受けることが重要です。
糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病は、網膜や視神経に影響を及ぼす可能性があるため、医師の指示に従い眼科を受診して目の状態を把握しておきましょう。
また、家族(両親や祖父母などの親族)に緑内障や加齢黄斑変性などの疾患歴がある方は、これらの病気になりやすい傾向があるため、注意が必要です。
40歳を過ぎたら
40歳を過ぎたら、1年に1回は眼科の定期検診を受けることが推奨されています。
例えば緑内障は40歳を過ぎると発症率が上がりますが、定期検診で早期発見・早期治療をすることにより、生涯視力を保てる可能性が高まります。
(参照:「日本緑内障学会多治見疫学調査(多治見スタディ)総括報告」)
白内障や黄斑疾患、網膜疾患なども、目の状態の変化を早期に発見することが非常に重要です。
目の健康を維持するためにも、積極的な定期検診を受けましょう。
まとめ
眼科の定期検診は目の健康管理に重要な手段で、目に異常がなくても受けることができます。
視力に問題がなく、困りごともなく、眼科を受診したことがない方は、なんて言って受診すればいいのか迷うこともあるかもしれませんが、「異常がないか検査したい」ことを伝えましょう。
自覚症状が出てからでは治療が難しい病気もあるため、早期発見のためには1年に1回の定期検診が非常に重要です。
この記事を参考に、受診すべきタイミングを確認してみてください。
タワーリバーク眼科では、定期検診で気になる症状があった場合は、OCT(光干渉断層計)検査や角膜形状解析などの機器を導入し、詳細な検査にも対応しております。
川崎駅西口直結でアクセスが良く通院しやすい環境で、ホームページから診療予約ができます。
眼科の定期検診にいつから行けばいいのか迷っている方、初めて検査を受けることに不安がある方は、タワーリバーク眼科へお気軽にご相談ください。